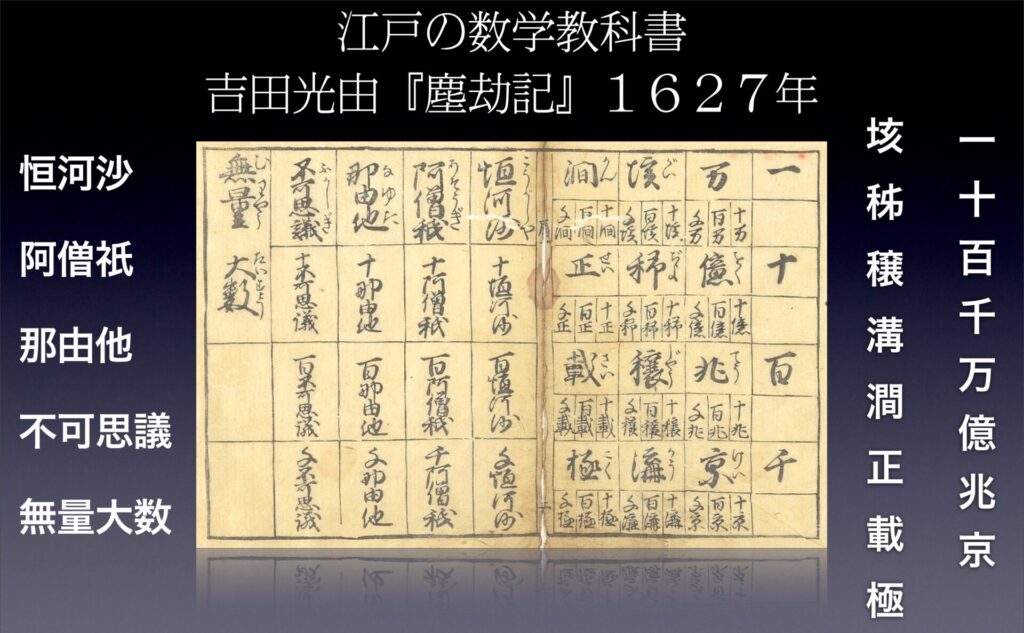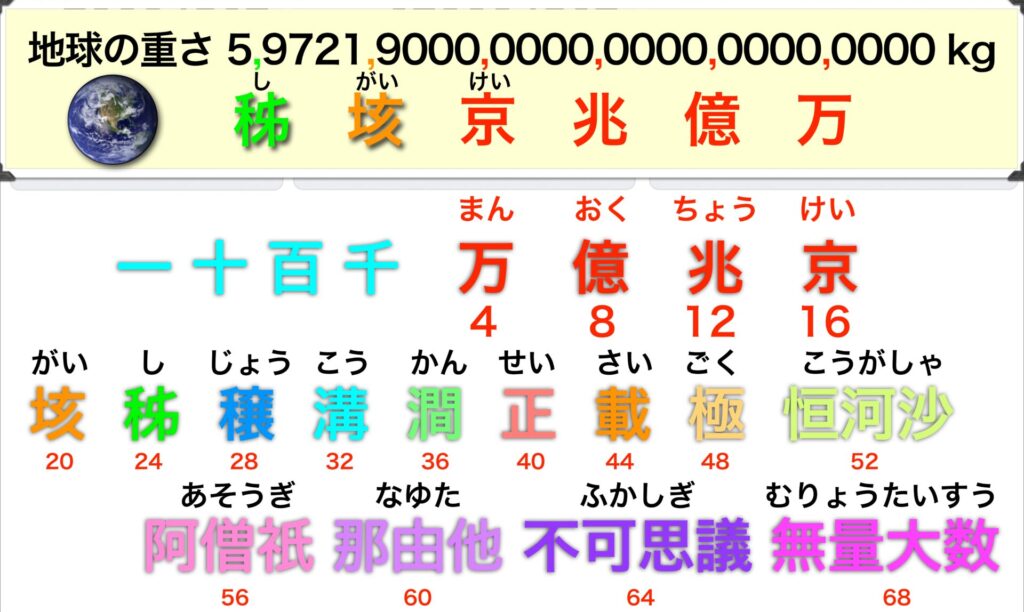Susumu Sakurai
Susumu Sakurai
Susumu Sakurai
Susumu Sakurai
Susumu Sakurai
Susumu Sakurai
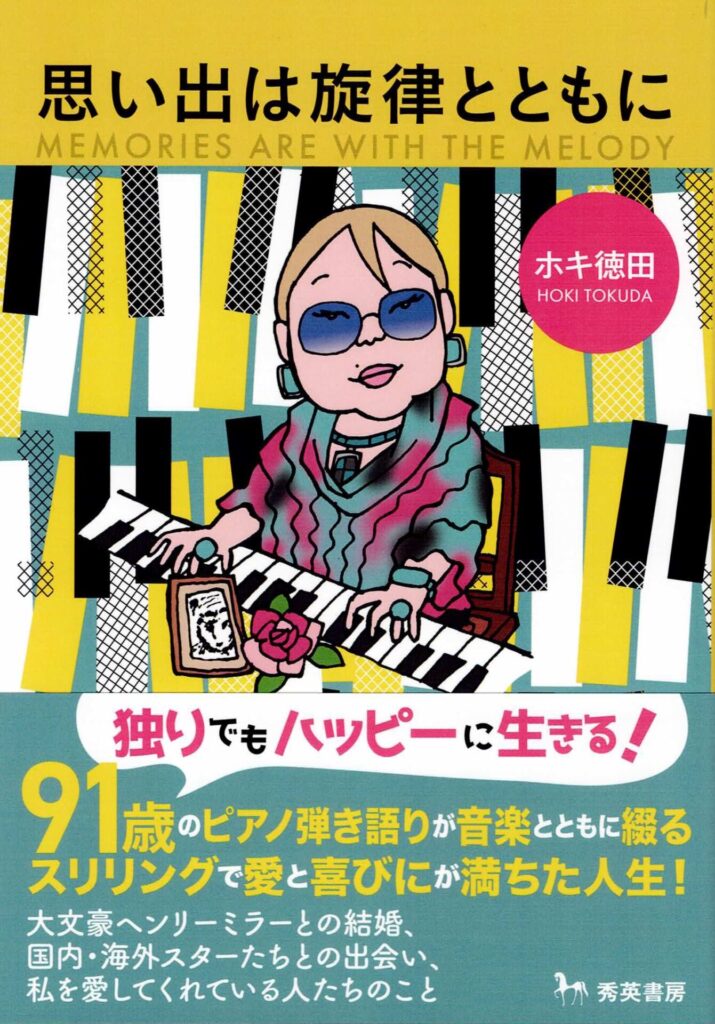
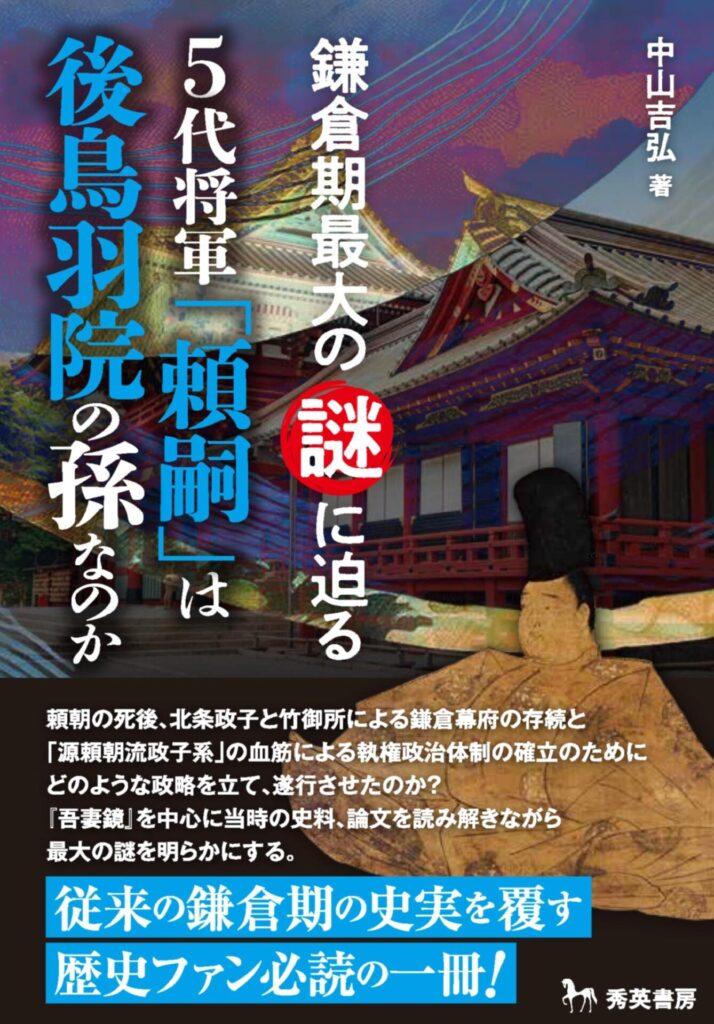
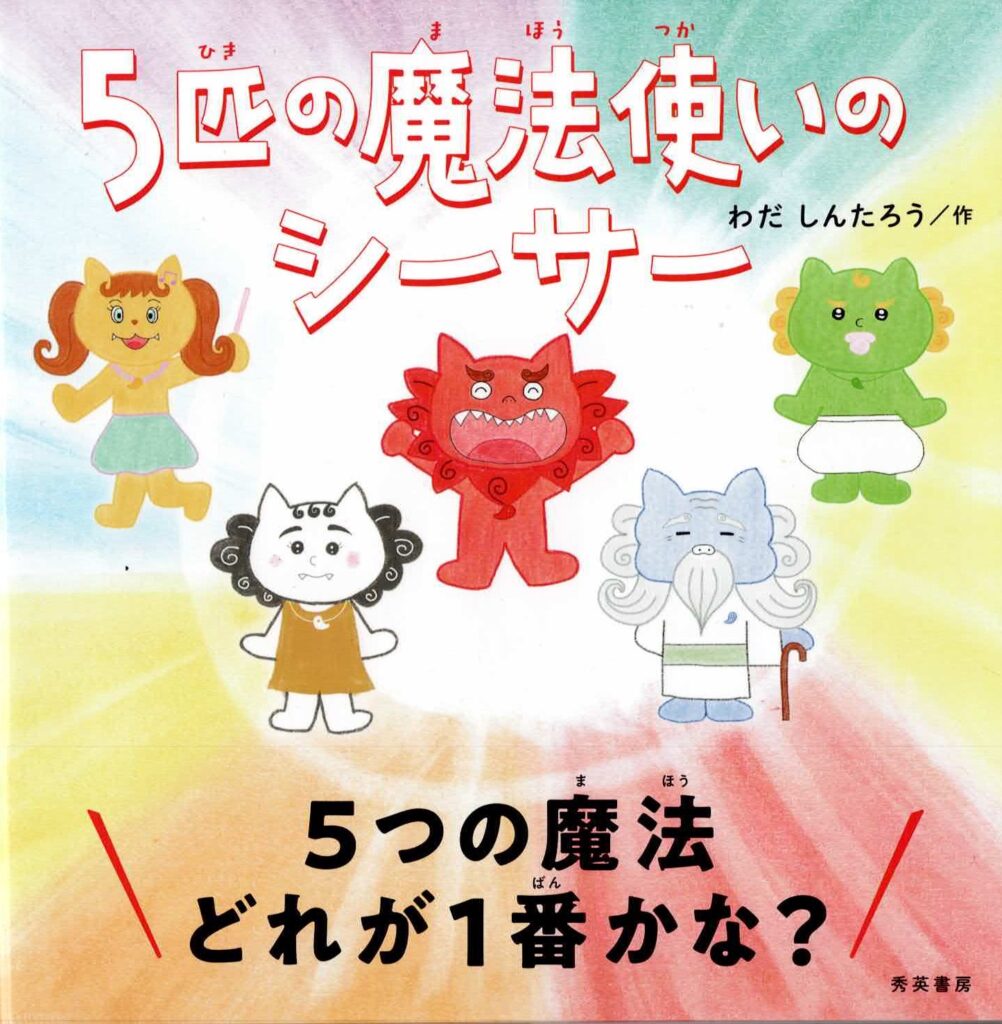
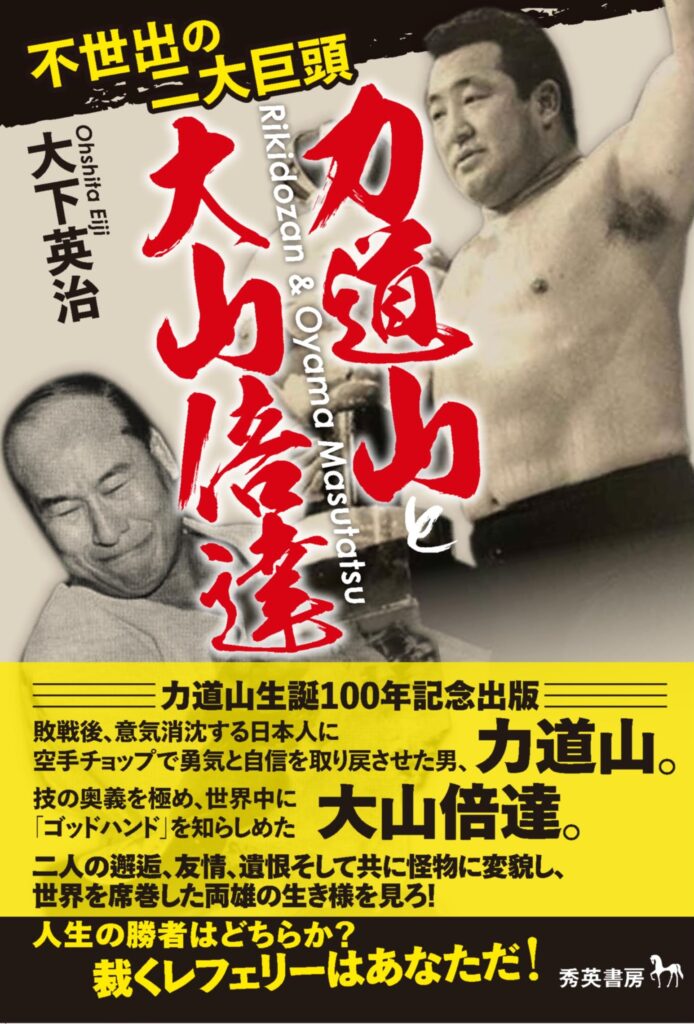
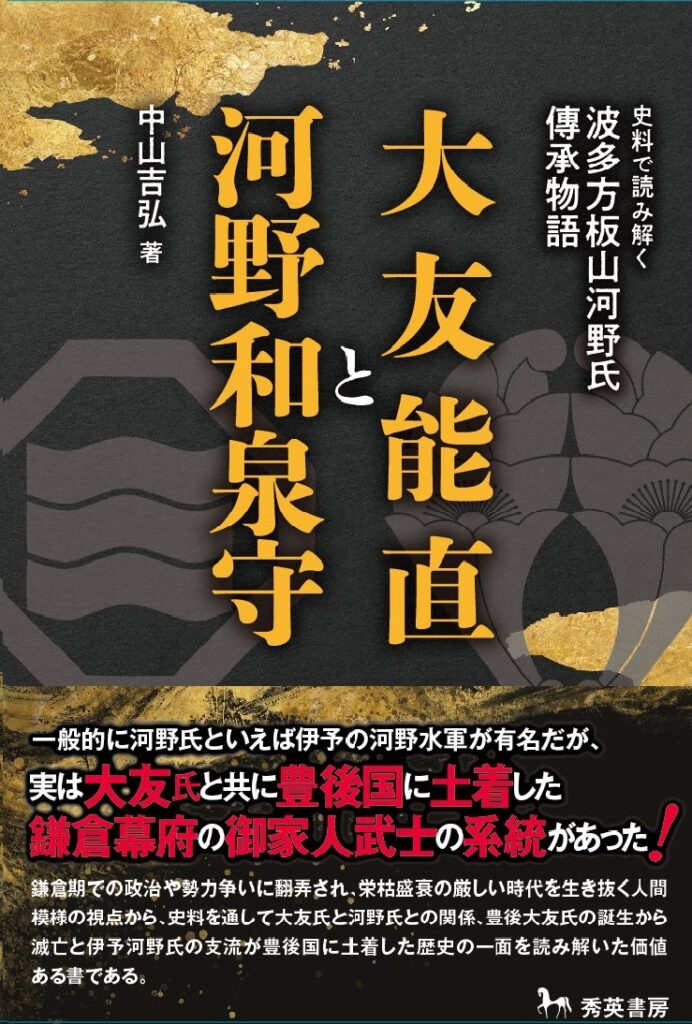
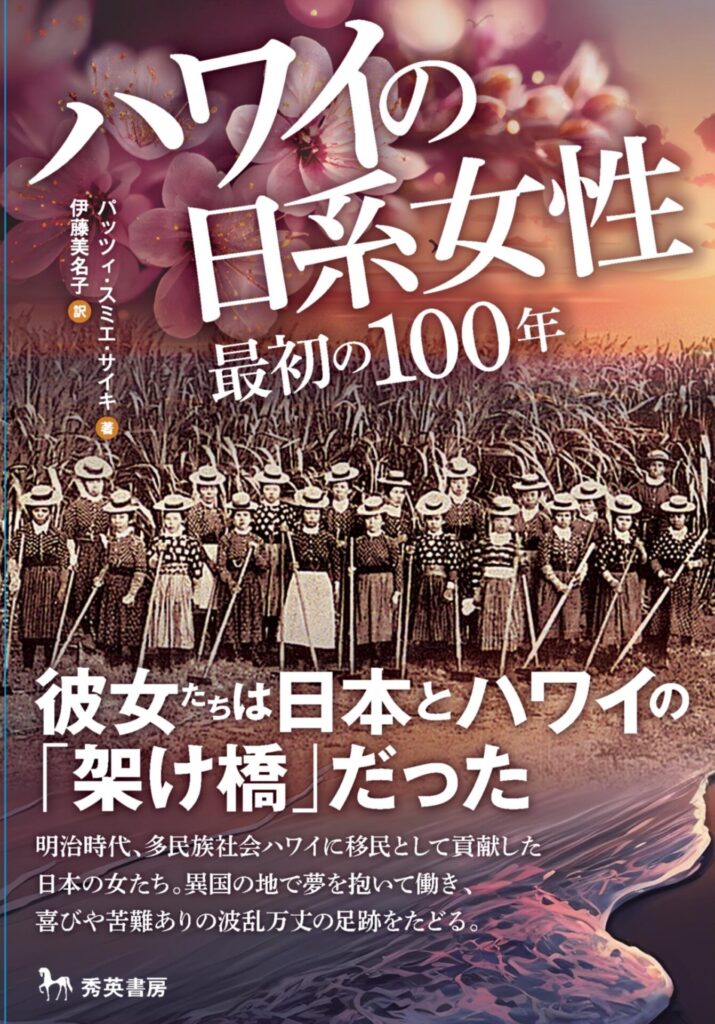
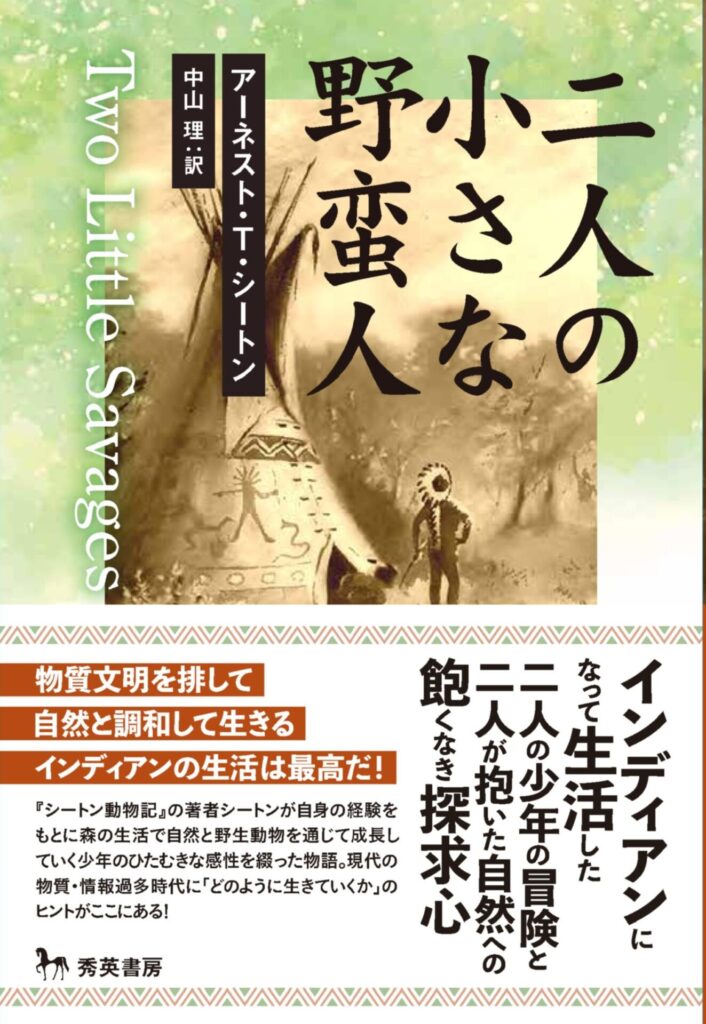
ページの向こうに、
新しい自分がいる。
さあ、まだ誰も知らない、
世界の始まりを覗いてみよう!


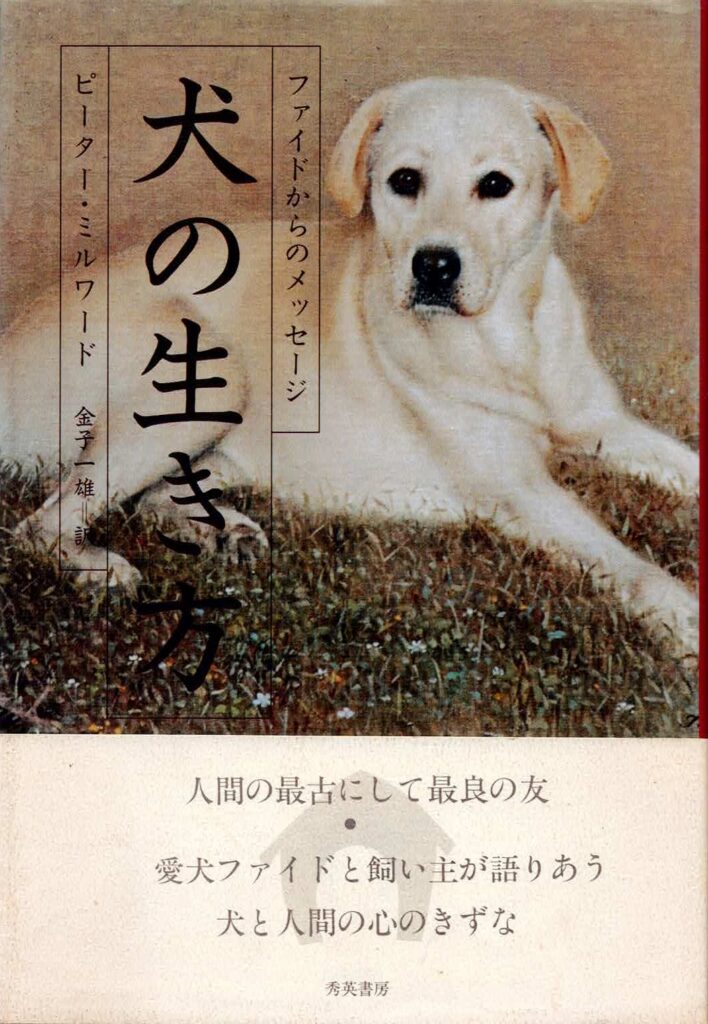

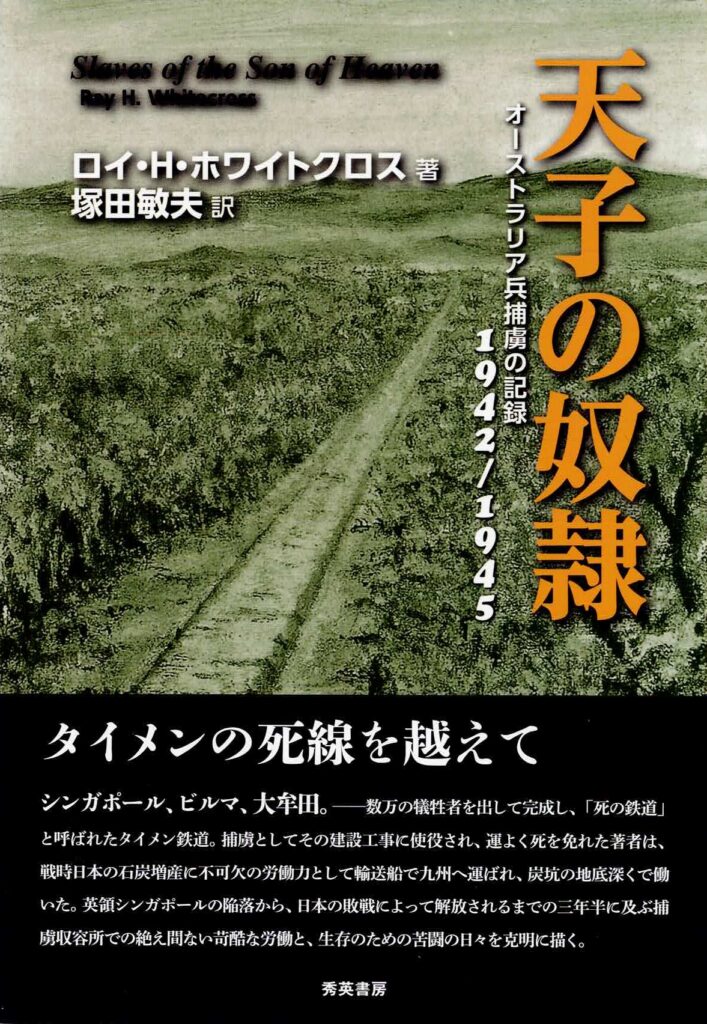

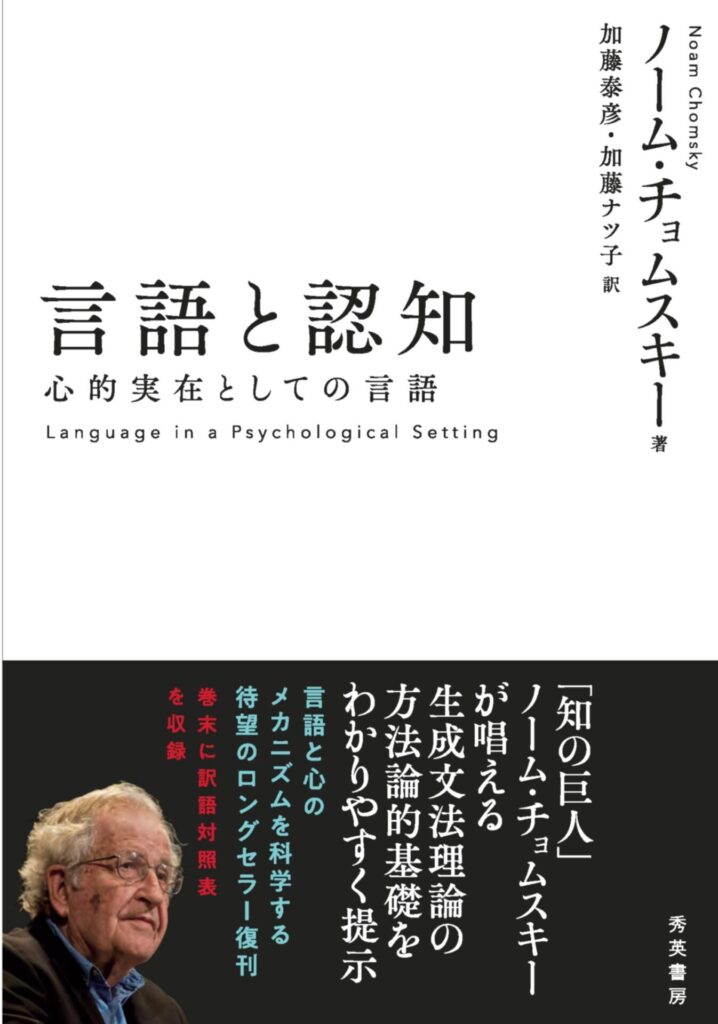
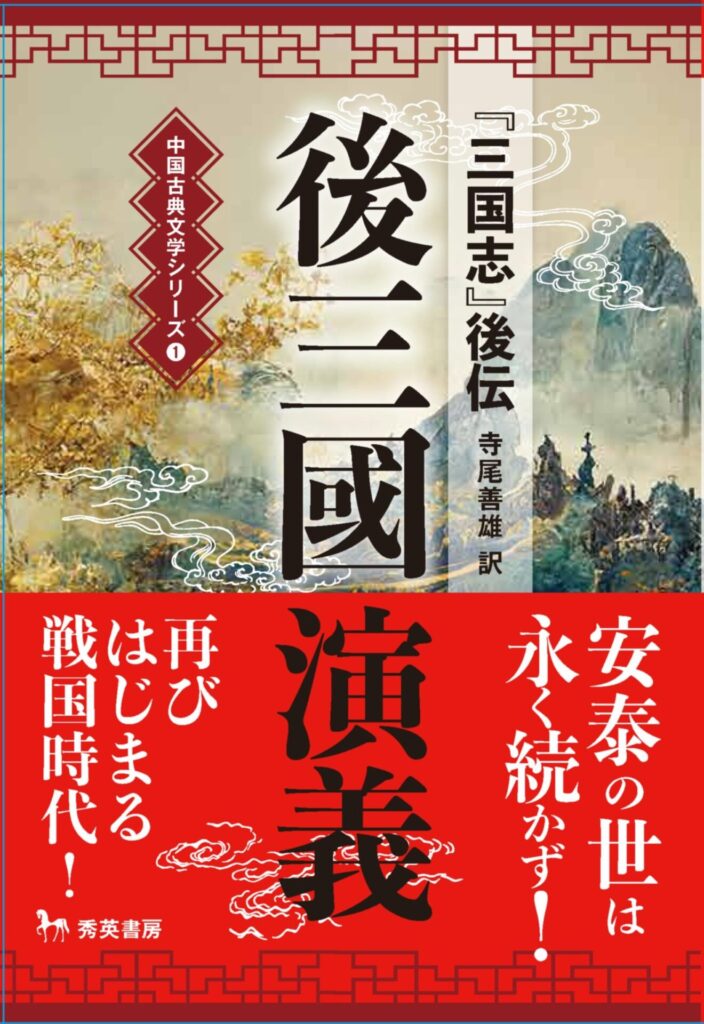
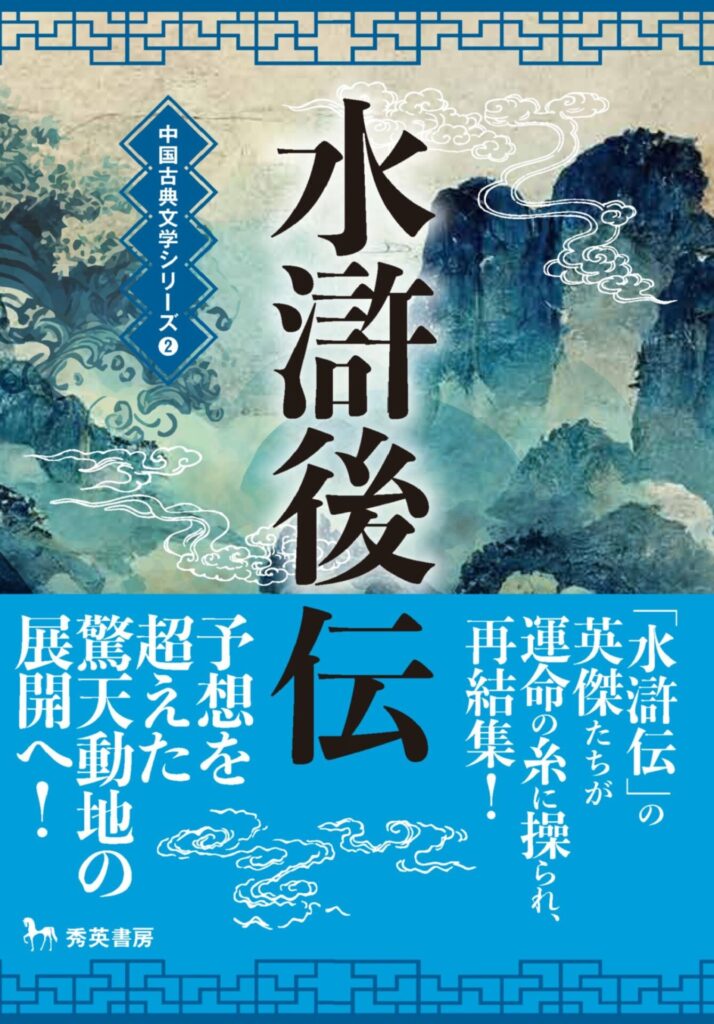
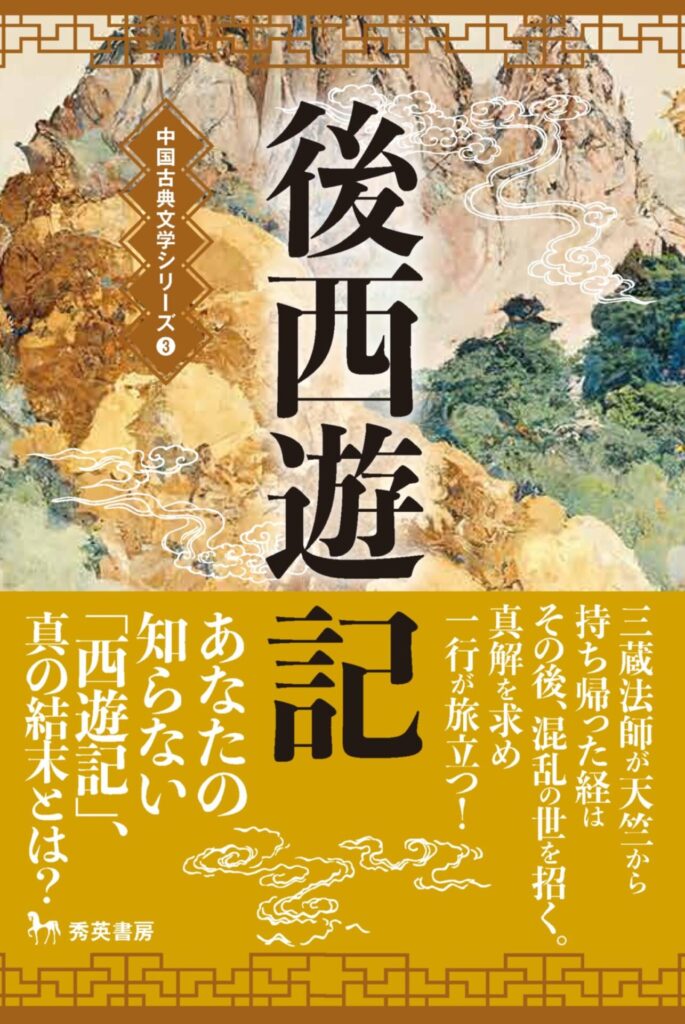
New books & Topics
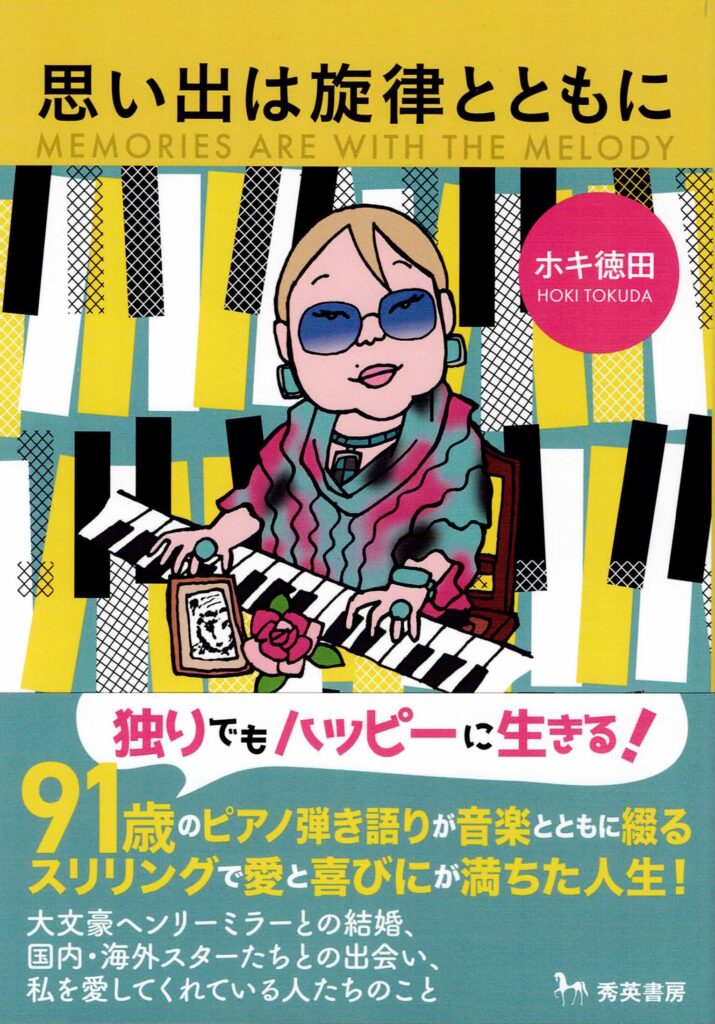
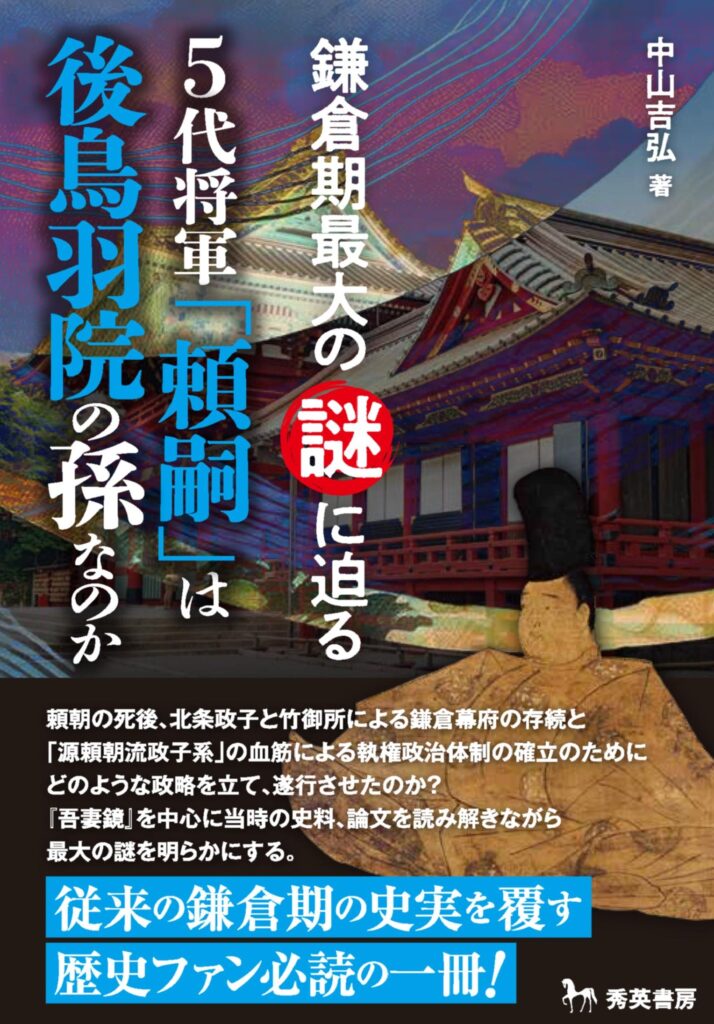
Web column

writer
キレンジャーの末裔


writer
桜井 進
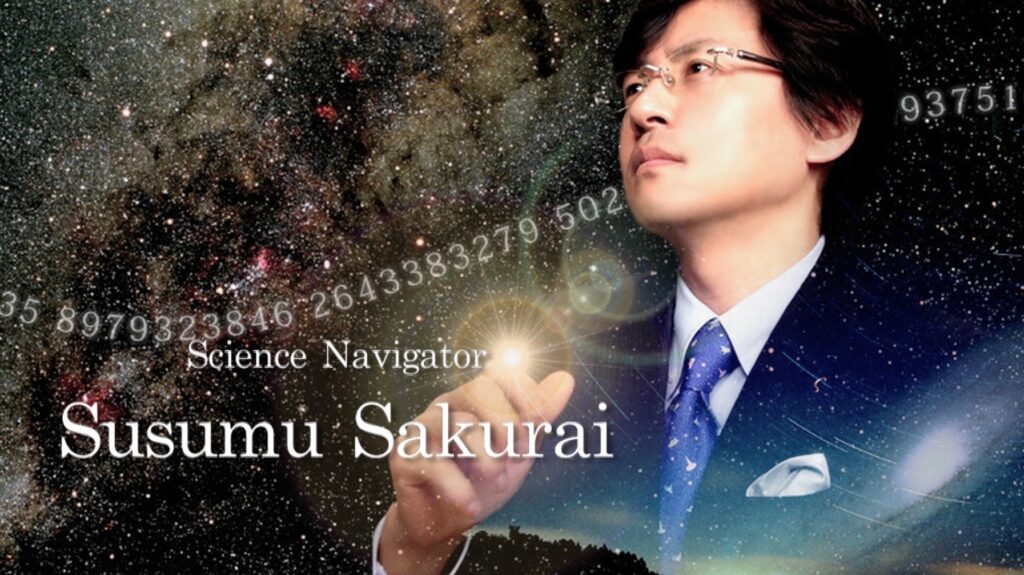
Lecture
By Professor
Susumu Sakurai
学校教育をもっと楽しく!
桜井進先生の算数・数学エンタメ講演会
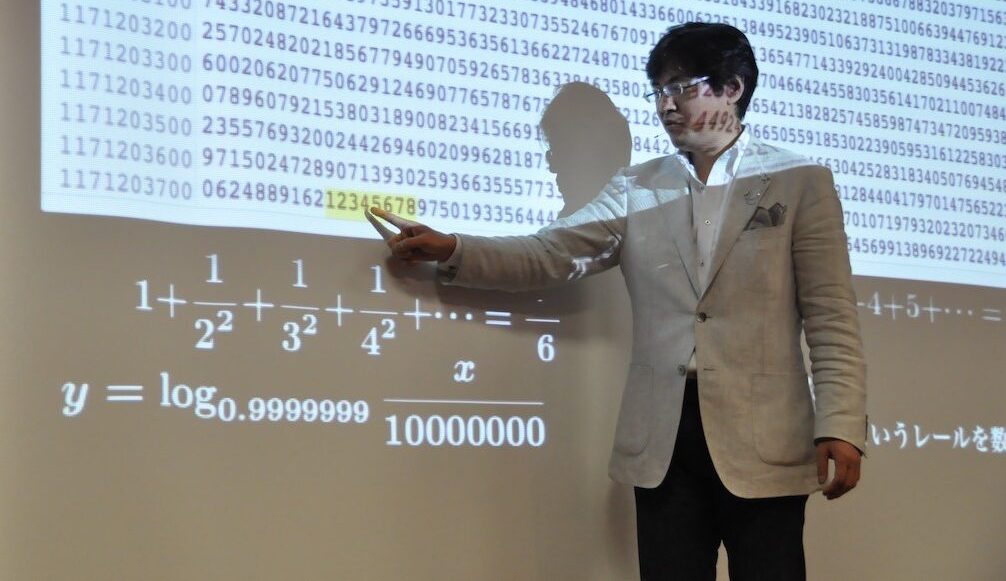

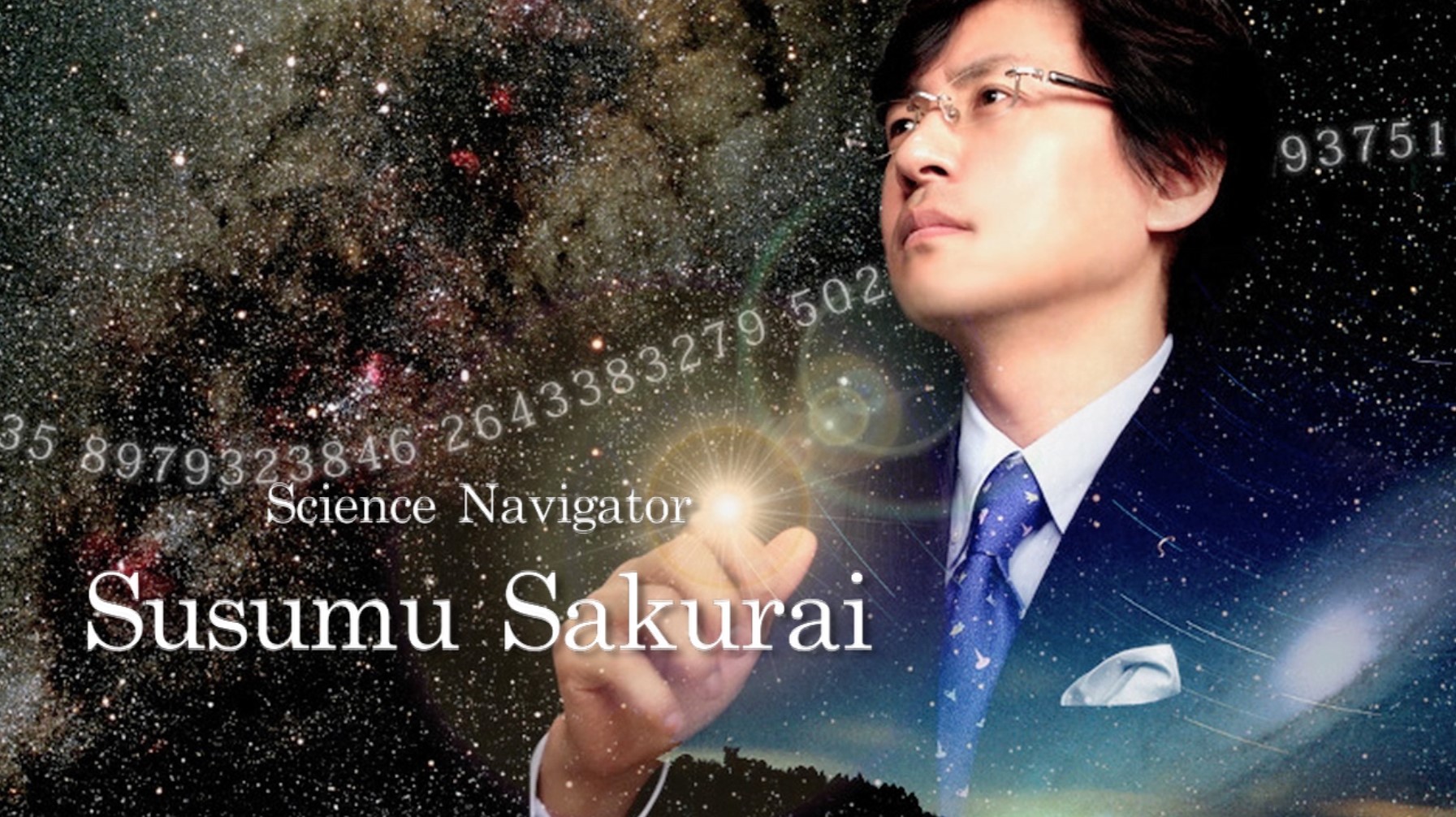


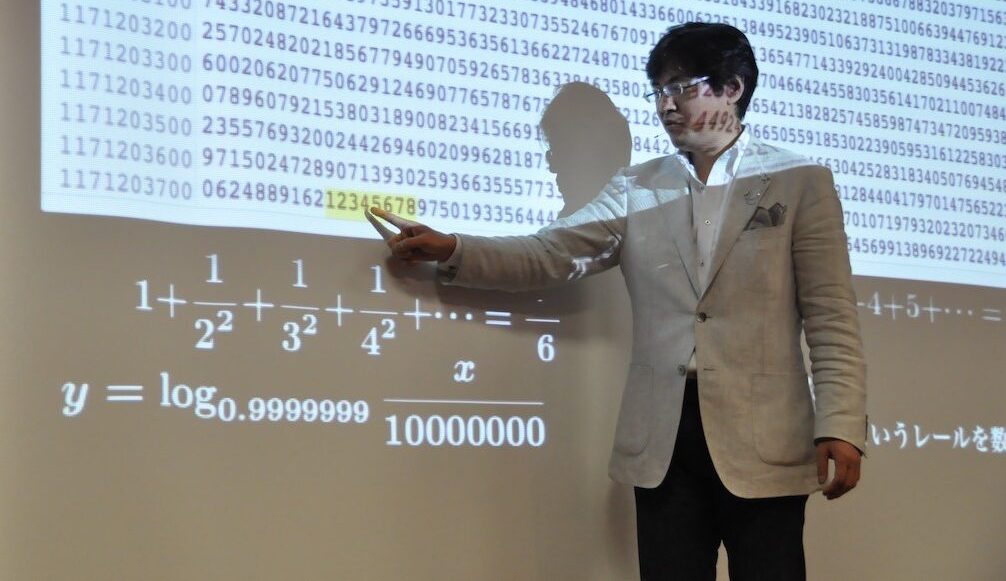

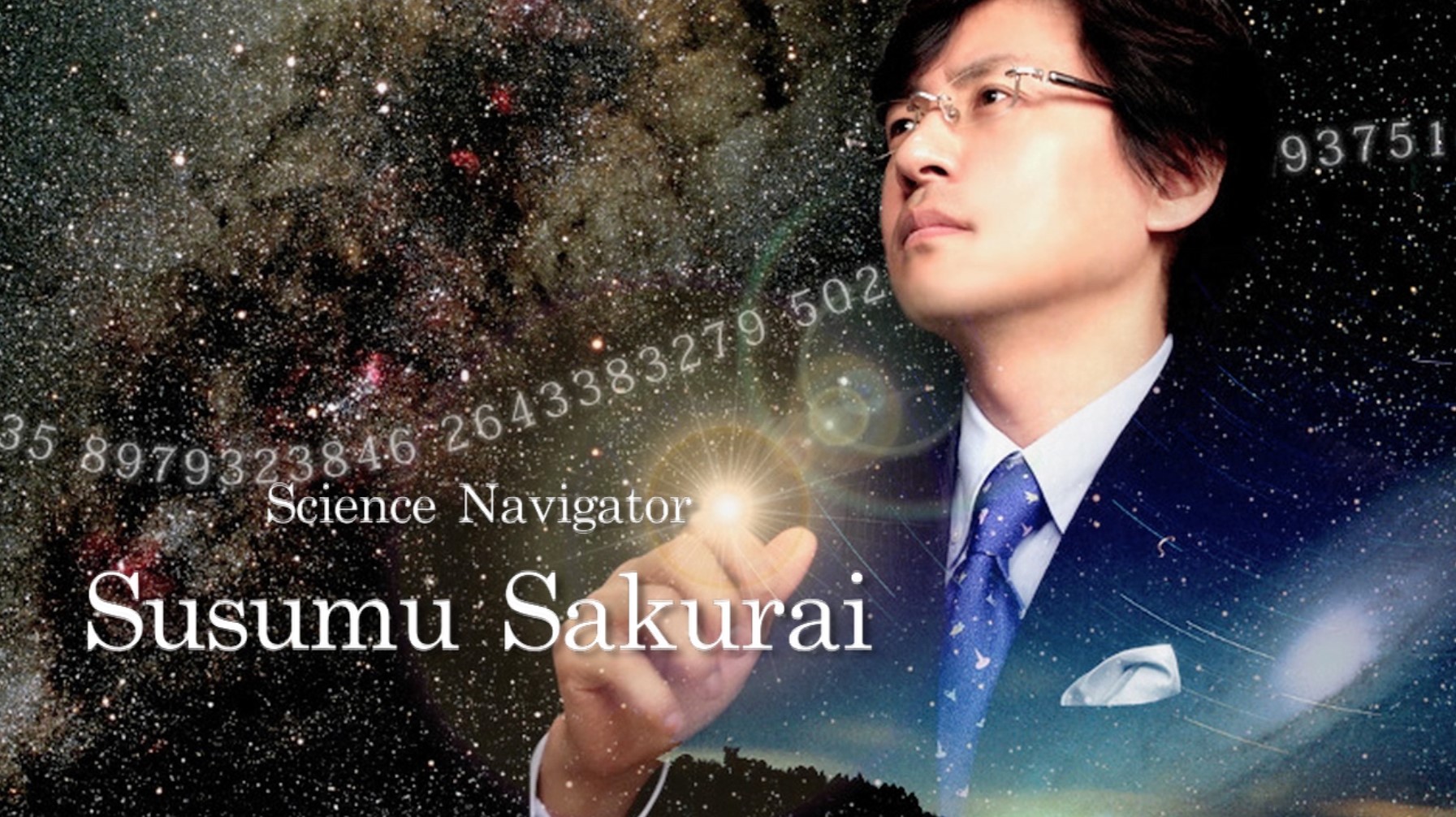
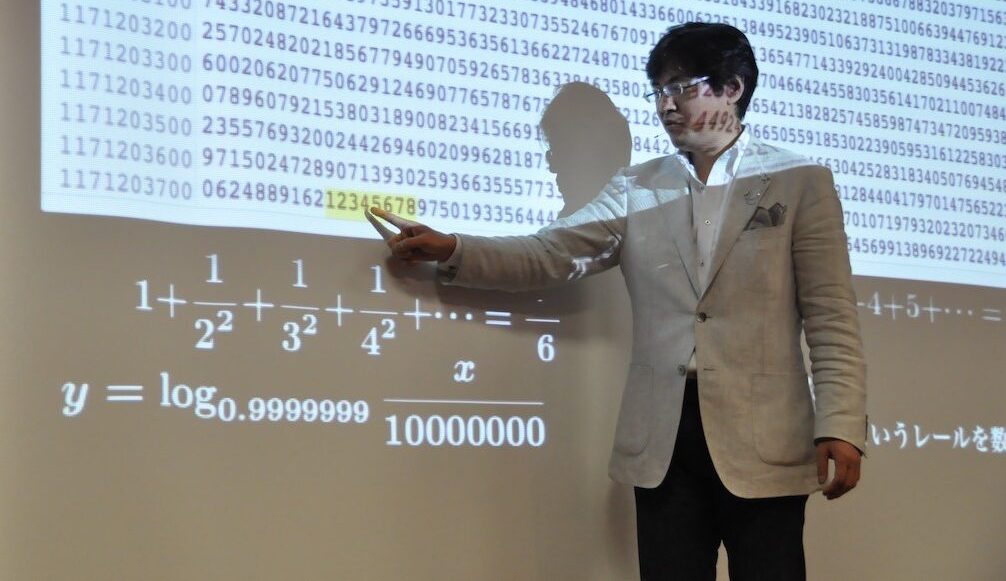

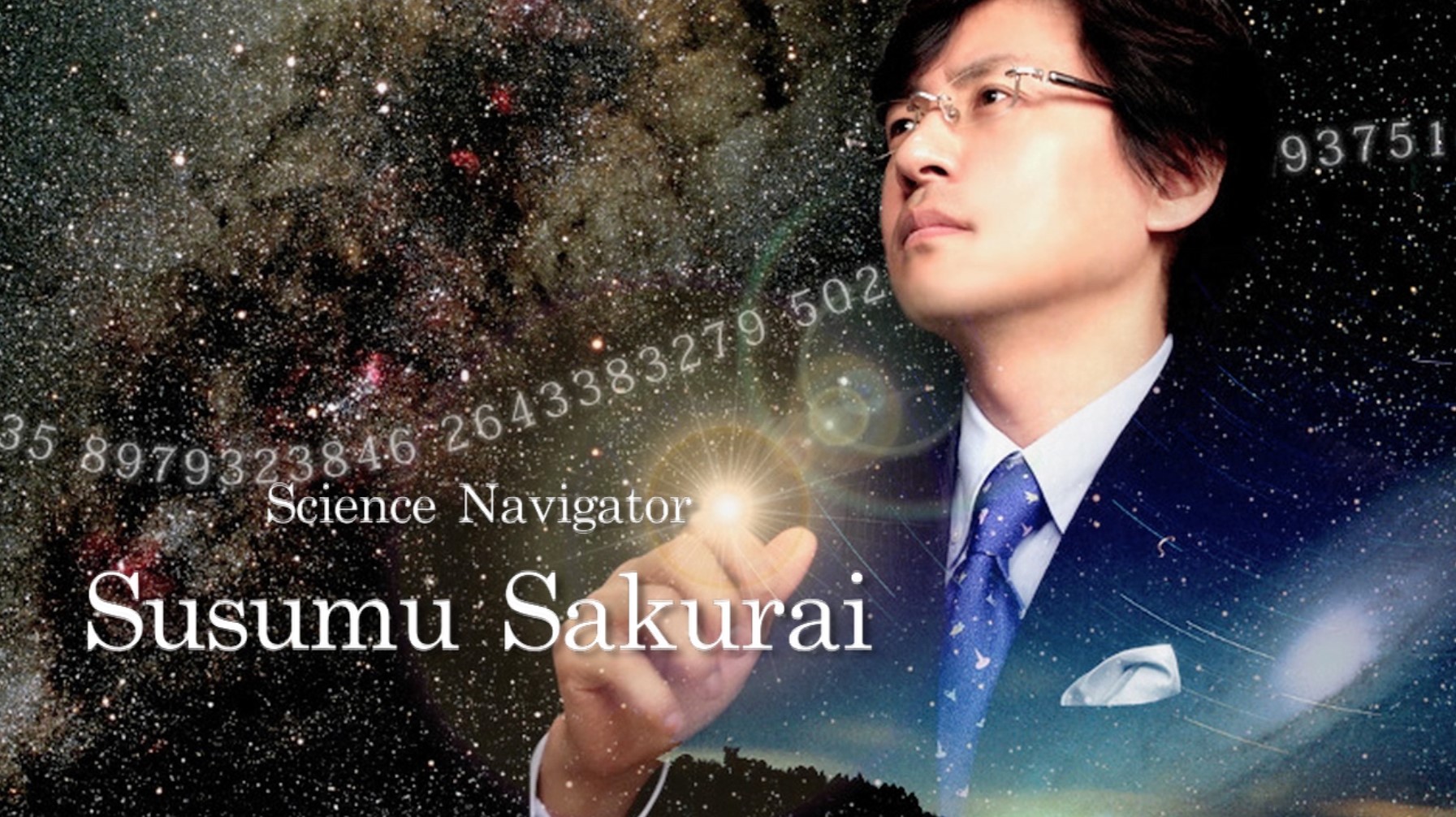


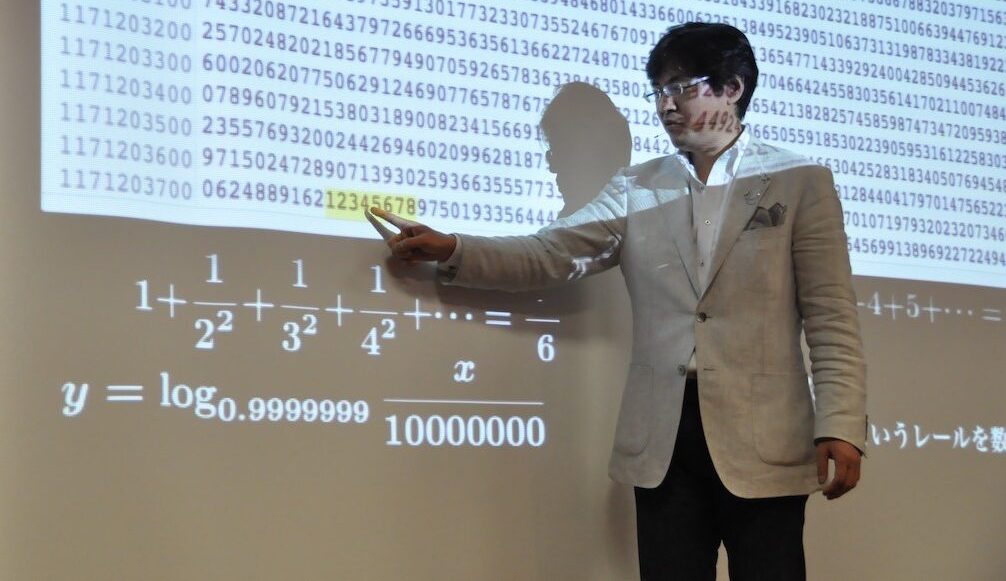

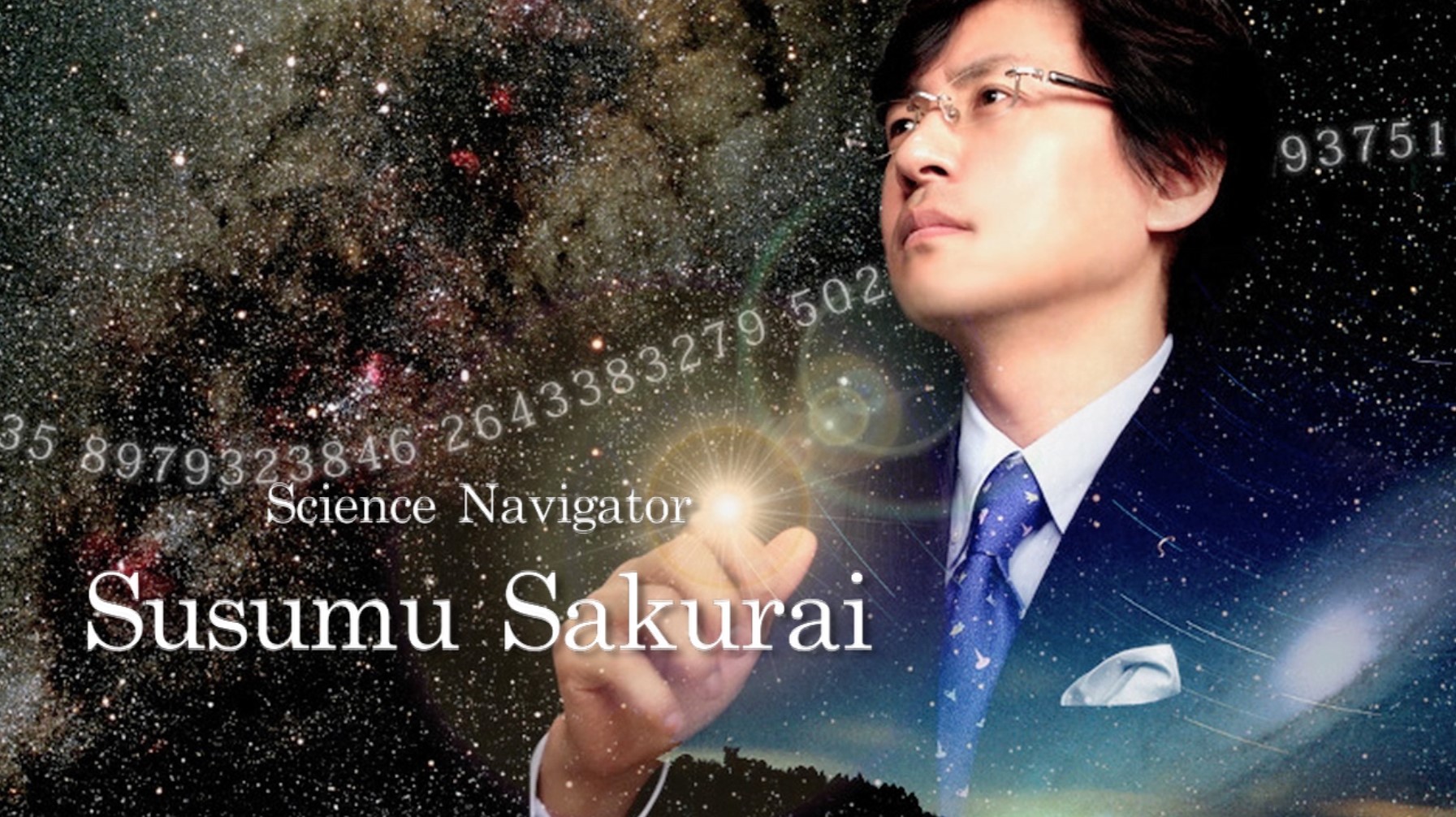
2025.09.16
三省堂書店経堂店に伺った後は、
無性にカレーが食べたくなります…。



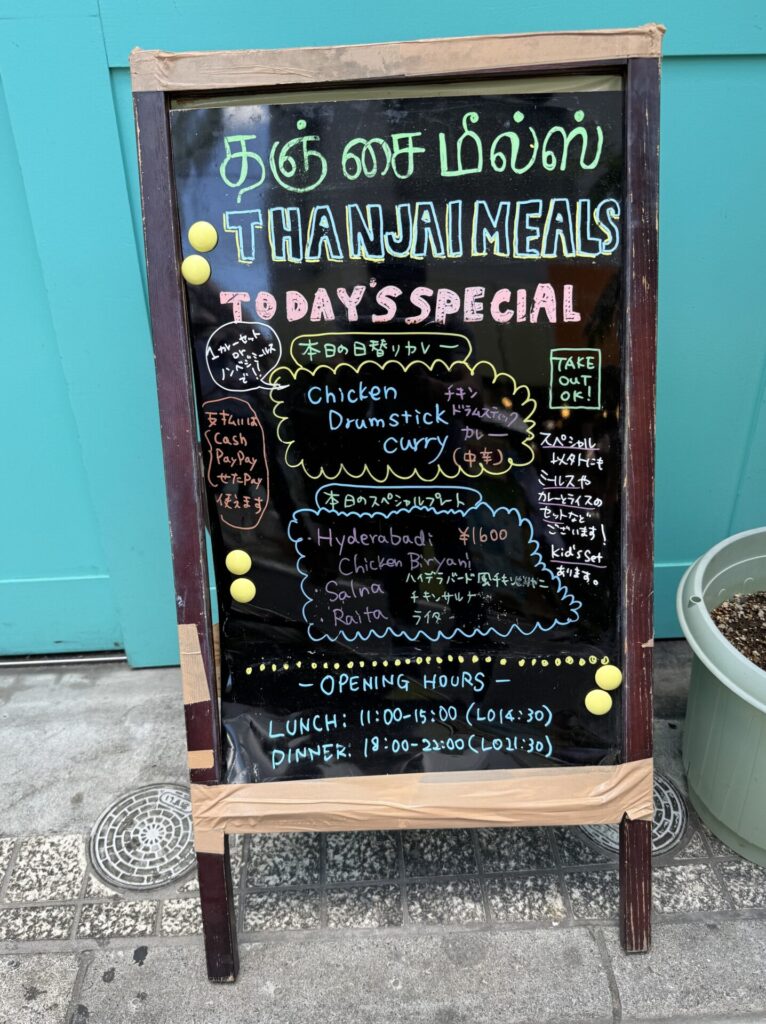
2026.2.26
第1話 まさしく“ 桁が違う” 規模! 大きな数と小さな数の話